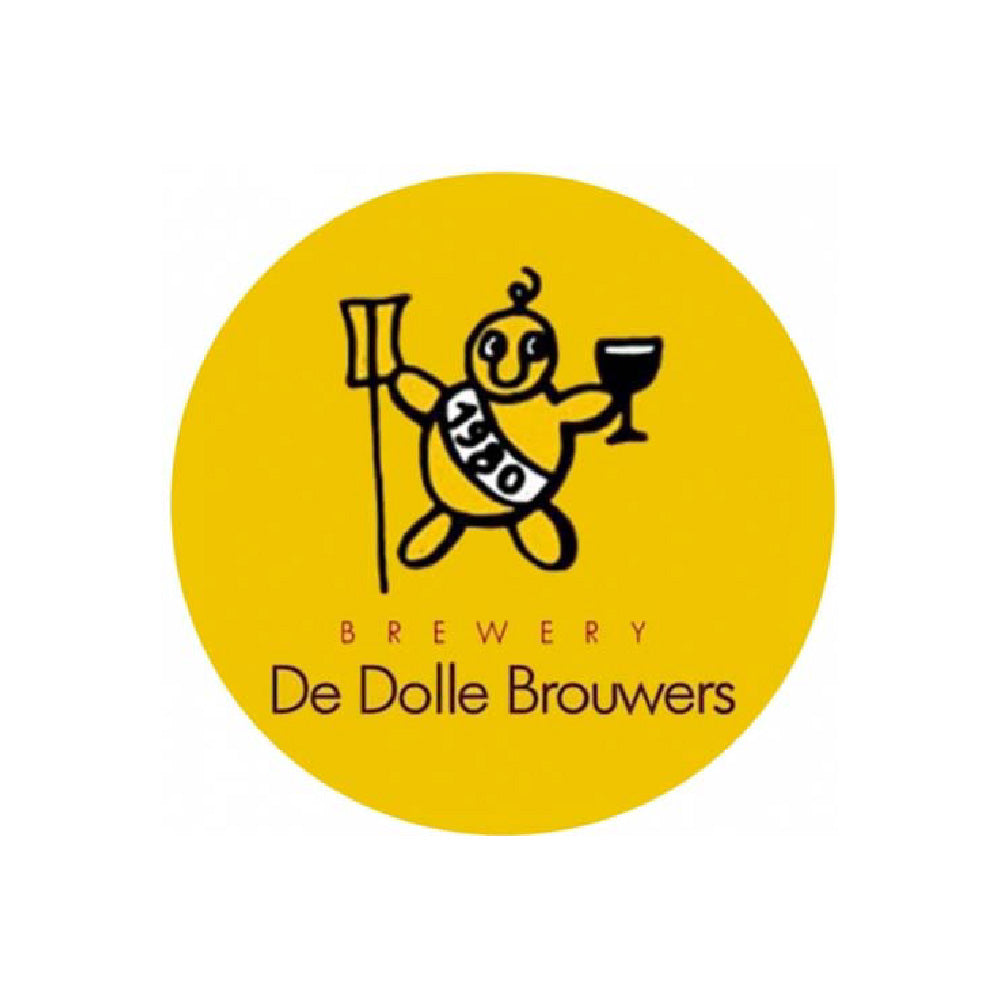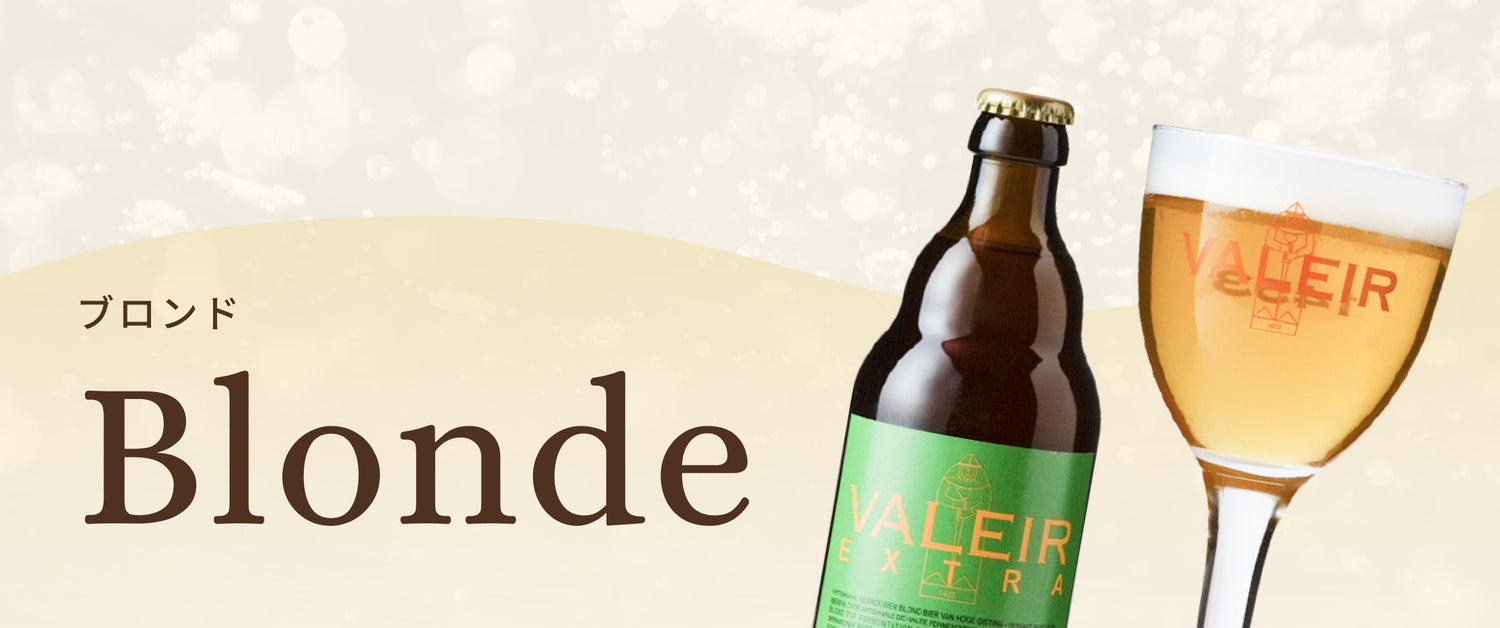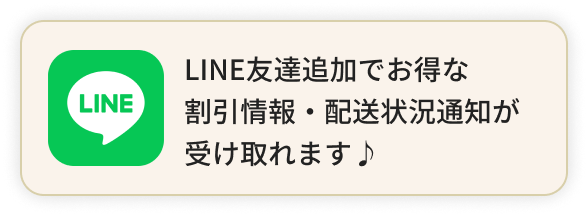Collections
-
-
-
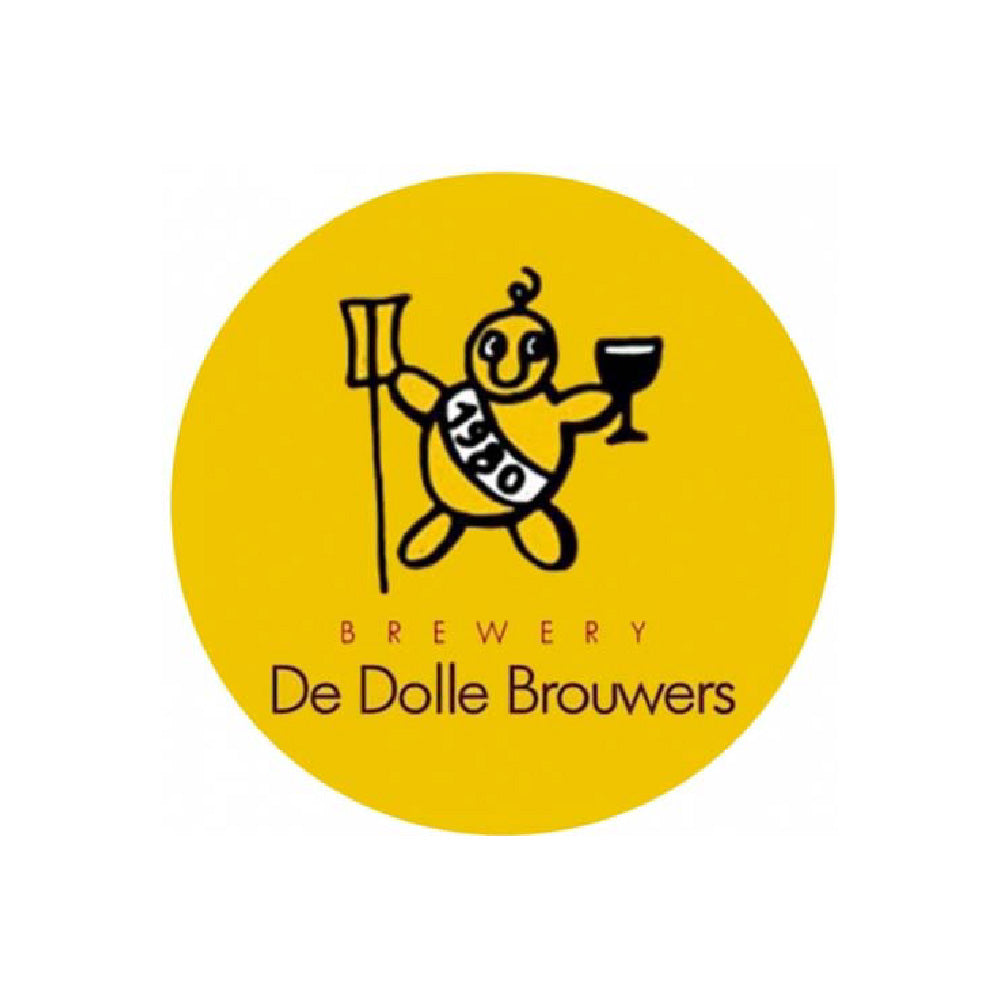
詳細を見る 今日はDe Dolle(デ・ドレ)醸造所のご紹介。 Esen(エセン)というベルギーの北西に位置する、小さな家族経営の醸造所です。週末のみしか醸造を行っていない、いわゆる“日曜醸造所”。De Dolleとは現地の言葉で「気ちがい」という意味だそう。趣味で始めた週末の醸造に夢中、という醸造家のクレイジーっぷりを皮肉ったもの。 そんな「ビール気ちがい」のデ・ドレ醸造所は、「ビールの鬼才」として知られており、週末になると地元だけでなく世界中からビール好きが押し寄せる、とても面白いスポットになるのです。 デ・ドレ醸造所は週末しか醸造しておらず、醸造所見学が出来るのは毎週日曜日のみ。醸造所のホームページに記載があるアドレスにメールをして予約をします(英語ツアー14時、オランダ語ツアー15時から)。 私が行った日の見学メンバーは、日本人2名、イタリア人カップル、アメリカ人の男性2人組という超インターナショナルな顔ぶれ。こんな片田舎のマイクロブリュワリーに文字通り世界中からビールファンが集まってくるのです。 醸造所の前で開始時刻の14時を待ちますが、10分経過しても醸造所はシーンとしたまま。不安になりながら扉に貼ってあった電話番号に電話したら、親戚の会合があって遅れているからちょっと待ってくれとのことでした(笑)。その約5分後に現れたのは、派手な靴とベルトを付けたとても人の良さそうなおじさん。この方がオーナーのクリスさんです。 クリスさんの本業は芸術家で、デ・ドレ醸造所のマスコットキャラクターであるOerbier man(ウルビアマン)や、ボトルのラベルのデザインも全て彼が手掛けています。一見、子供の落書きのように見えるこのキャラクター、醸造所に生息する酵母を描いているとか。醸造所の中にはクリスさんの描いた絵が沢山飾ってあり、他の醸造所とは全く違った面白い、独特の世界観が出ていました。 さて、クリスさんの到着でやっと醸造所ツアー開始。デ・ドレ醸造所は、1980年にHerteleer一家が閉鎖した醸造所を買い取り、趣味で始めた醸造所です。以前はエセンの町には6軒の醸造所があったそうですが、現在ではデ・ドレ醸造所のみとなってしまいました。...
-

デ ラ セーヌ醸造所について copyright philippe debroeもともとプロの音楽奏者を目指していたベルナルドが始めた、ブリュッセルの近くセント・ピーターズの町にある小さなセント・ピーターズ醸造所(現在はデ・ラ・セーヌに改名)にて2004年に、最初に醸造したビールがジネビアです。この地域はランビック(自然発酵ビール)を醸造するための自然発酵酵母が空気中に生息している事で知られるZenneゼネ川(ゼナ川)が流れています。このゼネ川をセント・ピーターズ付近の人達はなまってジネ川(Zinne)と呼びます。これがこのジネビアZinnebirの語源となります。ラベルのモチーフが川なのはそのためです。もともとのセント・ピーターズ醸造所の場所もランビックの醸造所の倉庫だったといいます。当初、彼はフランス語圏のブリュセロワーズ(ブリュッセルっ子)であり、フラマン語(オランダ語の方言)圏のこの町に自分達が受け入れられるかどうかを心配していたようです。地域に根ざそうと考えたものの、完全に手動の小さなビール醸造設備では醸造が追いつかなくなってしまい、彼は醸造所の移転を決意します。シント・ピーターズの町から離れる事となったため、彼は醸造所の名前も現在のデ・ラ・セーヌと変える事にしました。この名前もジネ川(フランス語読み)が語源となります。 ブリュッセルの移転を決意した後にも色々と問題があり、醸造所の移転をスムースに行う事ができず、2006年に次の醸造所が出来る事なく醸造所を閉鎖する事になります。その間、彼のパートナーであるイヴァンが修行していたデ・ランケ醸造所(イクスイクス・ビターなど醸造)を借りて醸造していました。2010年になんとかブリュッセルに醸造所が完成し、醸造を再会しました。彼らはランビック(自然発酵ビール)に非常に興味を持っており、ランビックとのブレンドなど若くも野心的な試みを行っています。弊社の菅原もパートナーとして醸造所に出資も行っており、深い関係を築いています。ベルギー・チョコレート・スタウトは醸造所と菅原の共同醸造として生まれました。 ブリュッセルにはランビックを醸造するカンティヨン醸造所以外に醸造所がなくなってしまっていたため、ブリュッセルの人たちの間でデ・ラ・セーヌのビールは若者を中心としてクールなビールとして受け入れています。毎年ブリュッセル一番の人気者小便小僧も彼らのビール「ジネビアZinnebir」をそのまま放尿するイベントも行われます。 閉じる
-

デ ランケ醸造所について 週末醸造家としてのスタート 名前の「デ・ランケ」はフラマン語(オランダ語の方言)にて「ホップが支えを伝って伸びる際に描く姿(らせん)」を指します。今はストライセ醸造所が借りているデカ醸造所を借りて醸造をしていましたが、エノー州ドッティニーに自らの醸造所を建設して週末に醸造を行うようになりました。ビール醸造を趣味で始めた、冷蔵機器を販売していたニノ氏と税務署職員のギド氏が二人で行う週末醸造所。今では世界のビール評論家やビールファンを唸らす味わいを常に作り出しています。辛口で知られるビール評論家のティム・ウェブ氏も唯一ブロンドビールで彼のビールに五つ星をつけています。ニノ氏はやっと会社を退職。それまでは醸造所(週末)への設備投資(本業)のために平日に仕事(副業?)をしていました。 生のホップをそのまま使用 通常のほとんどの醸造所はペレットと呼ばれるホップを圧縮した錠剤のような物を使用しますが、デ・ランケ醸造所は近隣のポペリンゲ産の生のホップをふんだんに使用することがこだわりであり、その中でも「グーデンベルグ」はドライホッピングという発酵中もホップを漬け込むという手間隙をかけて行います。そのドライホッピングも他社と違い、取り扱いやすいようにバックの中にホップを入れるのではなく、タンクにそのままホップを投入します。「ホップの花に含まれるタンニンが重要なんだ。ペレットを使うのは簡単だけど、質を下げるような事は何があってもやらない。じゃないと日本のみんなが飲んでくれなくなるでしょ?」とよく微笑みかけています。 ランビックのブレンダーとして 彼らはランビックの優秀なブレンダーとしても知られ、以前ローデンバッハ醸造所から酵母をもらって作ったビールに自分達で継ぎ足しながら出来る酸味あるレッドビールをベースにジラルダン醸造所ランビックとブレンドして、キュベ・デ・ランケ。レッドビールにチェリーを加えて熟成させたものとジラルダン・クリーク(チェリー)をブレンドしてボトリングしたデ・ランケ・クリークやなど、ビール愛好家、そして小規模醸造所達のあこがれの的となっています。 閉じる
-

デュベル モルトガット醸造所について 1871 すべてはヤン・レオナルド・モルトガット夫妻がブリュッセルとアントワープの間に位置するブレーンドンクの村で1871年にモルトガット醸造所を創業したことに始まります。20世紀はじめは、数ある3,000の醸造所の一つにすぎませんでした。試行錯誤の末、ヤン・レオナルドの上面発酵ビールは近隣地域までその評判が広まり、まもなくブリュッセルの中産階級まで彼のビールをこぞって買うまでになったのです。 1900-1918-2013 時は好況期。2人の息子のアルベールとヴィクトールが参加します。アルベールは醸造家、ヴィクトールはブリュッセルまでビール運搬と、明確に役割を分担していました。第一次世界大戦によって、ベルギーは英国と密接になりました。とくに当時非常に人気があった英国エールも第一次大戦によってもたらされたものの一つです。大人気の英国エールに触発されて、アルベールは英国エールをベースに新しい特別なビールを創り出そうと決意しました。アルベールは、最高品質の原材料だけを使用してあらたなエールを創造することを望みました。そこで英国に渡り、現地の醸造所の抵抗にあいながらも、とうとうスコットランドの醸造所から酵母のサンプルを手に入れました。今日使用されている酵母も、その酵母見本から受け継がれてきたのです。パーフェクトなレシピをつくるためにアルベールとヴィクトールの研究は続きます。第一次世界大戦の終結を記念して、新たなビールは「ヴィクトリーエール」と名付けられます。地元の試飲会で近所の靴屋さんのヴァン・デ・ワウワー衝撃的なアロマに感銘を受けて、「このビールは悪魔だ」と表現して以来、名称も「Duvel」に変更。当時のキリスト教国のベルギーでは、この時代に「悪魔」という名前を冠するのはかなりセンセーショナルでした。 1958-1960 「これまでのビールと全く違う」。これが話題を呼び、その評判は国を超えていきます。デュベルの国際的な評価が高まるにつれて製品レベルも成長します。このスペシャルビールに最初に魅了された国はオランダでした。1960年代には、デュベルの弟分的ビールが発売されました。その名もグリーンデュベル。発酵過程を1回だけにとどめることで、わずかな軽さが生まれ、近隣のバーやカフェで爆発的な成功を収めました。3代目モルトガット家(ベルトとマルセル・モルトガット、レオンとエミール・モルトガット)はユニークなビールにはそれに見合ったユニークなグラスが必要だと考えました。1960年代後半、はじめてのチューリップ型ブランドグラスが出来ました。ワイングラスを思い起こさせる画期的なこのグラスには、330ml瓶のビールの内容量すべてを注げなければなりませんでした。このグラスはビールの持ち味すべてを楽しんでもらうために、デザインされています。丸い形は、デュベルの最高の味わいと香りを堪能するために。トップに向けて細くなるデザインは、ガスを逃さないように泡をキープするためです。 2000- モルトガット家は醸造所の設備投資をコンスタントに行い、常に最高の品質を提供しています。そのおかげでデュベルは瓶内の品質が完璧に管理されたスタンダードとして世界的に広く認知されました。1990年代終わりには4代目が事業に参加し、デュベルを世界的企業に発展させる決意をしました。1923年のデュベルの出荷数はかぞえるほどでした。今日、デュベルは世界各国60カ国以上でビール通の方々にお楽しみいただいています。そして今も、オリジナルレシピに基づき長い時間をかけてビールを醸造し続けています。 (www.duvel.beより抜粋。一部加筆) 閉じる
-

デュポン醸造所について セゾンビール エノー州は、セゾンビールを醸す醸造所が数多く存在する。同じくエノー州でセゾンビールを醸造するシリー醸造所と同じ1850年の操業となります。セゾンビールというのはベルギーきっての穀倉地帯であるこの地域で農家が農作業中の喉を潤すために手の空く冬場にビールを仕込んでいたものが起源で、農作業中や仕事後に飲むためであったため比較的低アルコールの物が多い。 セゾン・デュポンは現在セゾンビールを代表する銘柄でありこのビールを手本として作られるセゾンビールも数多く存在する。セゾンビールはもともと赤みがかった色のものも多かったがこのビールによって現在はブロンド色のセゾンが非常に増えている。(シリー醸造所参照) Brasserie Dupont デュポン醸造所は「セゾン」を中心と したイーストに特徴を持つアルチザンなクラフトビールを造り続けています。その歴史は1759年から続くリモー・デリッダー農場醸造所 を初代ルイ・デュポンの父親、アルフレッドが買い取ったところから始まり、現代表兼、醸造責任者であるオリビエ・ ドゥデケール氏は4代目にあたる。夏の間、季節労働者の疲れと渇きを癒すために 造られていたビール「セゾン」。醸造所を代表するセゾンデュポンは世界中からお手本とされており、セゾンビール:ファームハウスエールのルーツと言っても過言ではありません。 閉じる...
-

詳細を見る 修道院にて作られるトラピストビール トラピストビールとはトラピスト派の修道院で作られるビールです。アビィビール(修道院ビール)とトラピストビールの違いがあり、トラピストビールは修道院で修道士が醸造に関わり作られています。修道院ビールは実際に存在する修道院や昔、存在した修道院の名称を借りて民間の醸造所が作っています。修道院でお酒??と思われる方もいらっしゃるでしょうが、昔から自給自足でワインや他の食料(チーズ等)を作って生活していました。中世から修道院は旅人の宿泊先でもあり、醸造したお酒を振舞っていたとの話もあります。同様にビールも修道院で作られていました。トラピスト派だけがビールを醸造していたのではなく、昔はトラピスト派以外のベネディクト派等でも作られていましたが、次第にビールを作る修道院は減っていきます。現存するベルギーのトラピストビールの修道院は6つです。シメイChimay ノートルダム サン・スクールモン修道院オルヴァルOrval オルヴァル修道院ロシュフォールRochefort ノートルダム サン・レミ修道院ウエストマレWestmalle ウェストマレ修道院ウエストフレテレンWestvleteren セント シクステュス修道院アヘル アヘル修道院※オランダのラトッペは修道士が醸造に関らなくなり、1999年にトラピストビールの称号を剥奪されましたがその後また修道士が醸造に関わるようになり、トラピストビールとしてまた認められました。トラピストビールは他の修道院ビールに紛れて、ブランドが失われてしまう事がないように特別なロゴが印刷されています。(※一部を除いてウエストフレテレンはラベルがないのでついていません)一つ注意しなければいけないのはトラピストビールとは、味の分類ではありません。ですから様々な味わいがあります。しかし、トラピストビールの味わいはすべて最高の物ばかりです 閉じる
-
-

ドリー フォンティネン醸造所について 三つの泉 ドリー・フォンティネンとはオランダ語で「三つの泉」を意味する。ランビック作りに必要な自然酵母が多く住みつき、多くのランビック醸造所が軒を連ねるブリュッセルの南西ペヨッテンランドのベルセルの町にて操業している。オード・ベルセルというブレンダーもあるランビックの町だ。ベルセル城も大変美しい。1953年に創業した父から息子兄弟が経営を引き継いで経営しており、兄のアルマン氏がランビックの醸造を弟のギド氏が醸造所直営のレストランを担当している。直営のレストランではアルマン氏の作る様々なランビックのブレンドに加えてそれらを使ったビール料理を楽しむことができる。 ランビックのブレンダーから 1998年 訪問記 ドリー・フォンティネンは「3つの泉」という意味で、ランビックのブレンダー兼メーカーだ。1953年にランビックのブレンダーとして設立された。60年代には併設のレストランを開店し、99年にはオリジナルのランビックの醸造をスタート。時代の流れにより巨大ビールメーカーに淘汰されていくランビックメーカーが多いなかで、このランビック醸造開始はベルギーでは80年ぶりの醸造所設立となったそう。原点回帰というか、こういう古き良きものを見直す流れは今後も続いて欲しいと思う。 ちなみにブレンダーとしてのドリー・フォンティネンは、ブーン醸造所、リンデマンス醸造所、ジラルダン醸造所という3つの名門醸造所から原酒を購入しそれをブレンド、瓶詰め後、10ヵ月間瓶内熟成させているそう。オードグーズ、オードクリーク、ランビック、ファロなどを造っている。 さて、見学についてですが、「要予約」とホームページに記載があったため事前連絡するも返信なし…。近くのオード・ベルセル醸造所は予約不要で隔週の土曜日の12時半から英語ツアーを開催していたので、そのあとに突撃してみることに。醸造所の手前には小さなショップがあり、裏手にはレストランが。レストランでは一般流通していないランビックを飲むことが出来るそう。 ショップには誰もおらず、醸造所の前で若いお兄さんが休憩していたので、声を掛けてみることに。すると、ちょっとだけだったらいいよと醸造所の中に入れてくれた。所要時間は5分程度でざっと英語で各設備の説明をしてくれ、樽出しの11カ月の若いランビックの試飲(度数4%)も無料でさせてくれた。匂いをかぐとかなりの硫黄臭が…!温泉街のゆでたまごのような匂いだけれど、やっぱり癖になる。 醸造所自体はこぢんまりとしているが、今まで見たランビックの醸造所と異なり近代的な設備が入っていた。調べてみると2009年に貸与されていた醸造設備の返却を余議なくされ、醸造を一時断念する事態に陥っていたよう。看板に2013年に新しい醸造所オープンと書いてあったので、一時中断の後、この時に新規設備を導入したみたいだ。ランビックの伝統的な型にとらわれない造り方をしているようで、醸造所にはホップのペレット(ホップを粉砕して固めたもの)が置いてあった。通常、ランビックには1~3年ほど乾燥させた古いホップの花をそのまま使うと本で読んでいたので珍しいなぁと思ったのだけど、残念ながら、非ペレットのランビックとこのランビックを同時に飲み比べたこともないし、そもそもまだ勉強不足なのでこれがどう味に影響しているのかは不明なところ…。...
-
-

-

ヒューグ醸造所について 東フランダース州の小さな町で ベルギー東フランダース州の州都であるゲントの隣町「メレ」の町「アップルホック」に位置し、1654年にはこの場所でビール作りが行われていたとされています。1906年レオン・ヒューグが「デン・アップルホック醸造所、製麦所」を買収します。1936年にアップルから「ヒューグ醸造所」へと名前を変え、新たなる醸造ルームの建設を始めました。1939年に建設が終わったその建物はつい数年前まで醸造のために使用される事となります。 ジョン・デ・ラートとデリリウム・トレメンス 様々なスペシャルビールを醸造するベルギーもピルスナータイプのビールに押される中、ヒューグ家と結婚して醸造所を継いだジョン・デ・ラートは1990年に「デリリウム・トレメンス」を発表し、ベルギーを代表するゴールデンエールとして世界中のビール愛好家から認められるようになりました。 デリリウムカフェの誕生 ジョン・デ・ラートは息子である現オーナー アラン・デ・ラートに醸造所を譲りもう一つのい夢であった「デリリウムカフェ」をオープン。あっという間にベルギーで一番有名なビアカフェとなりギネスブックにも世界で一番ビールの種類を取り扱う店としてギネスブックに認められました ヒューグ醸造所とブラザーフッド 閉じる
-

ファントム醸造所について Brasserie Fantôme ファントム、その名もお化け醸造所。ベルギー南部アルデンヌの森、ソワの街に位置する生産量もごく少量のマイクロブリュワリー。この近くのお城には昔から夜になると幽霊が出るという言い伝えがあるそうです。しかしラベルに書かれているお化けはとっても愛らしく、かわいいキャラクターが描かれています。 孤高の醸造家ダニープリニョン、彼は自分が納得できてかつ地元に貢献できるようなビールが造りたくて醸造所を始めたそうです。彼が造るビールはとてもユニークで個性的、その人柄がビールにもよく表れています。季節の花やハーブ、スパイスなどを使い、唯一無二の味わいを作り出します。でも詳しくは秘密。ある種カリスマ的な人気を誇るファントム醸造所は、世界中の醸造家からコラボレーションのオファーが絶えないそうですが、ダニーはいつでもマイペース。あまり多くのコラボレーションはしないそうです。 代表銘柄の「ファントム」はイチゴのようなアプリコットような、また花を思わせるようなお化けのように現れては消える独特な香りと味わい。一度取り付かれたら魅了されること間違いなし。日本への入荷もなかなかできません、見つけたら買い!な醸造所です。 閉じる
-

フランダース・レッドビールについて アメリカや世界のクラフトビールの手本となったフランダース・ブラウンとレッドビール レッドビールとは 西フランダース州で造られている赤褐色のビールの事で乳酸発酵させ、オーク樽での長い熟成させたビールをブレンドさせて醸造されます。特別な酵母とオーク樽の微生物の働きで酸味とブドウのような甘みももちあわせます。西フランダース州がレッドビールを多く生産するのに対し、東フランダース州ではブラウンエールが醸造されています。世界のクラフトビール界でサワービールが世界を席巻しているのはベルギーのランビックやレッドビール、ブラウンビールから始まっています。 ブラウンエール 東フランダース州で造られている赤褐色~茶褐色のビールを言います。ブラウンビール(エール)というとイギリスの茶色のビールを連想されると思いますが、これはベルギービールの中のみの特殊な分類となり、味わいはまったく異質の物となります。金属タンクでの数ヶ月の熟成により、酸味とフルーティーな味わいが特徴の伝統的なビールです。 数少ないブラウンビール ブラウンビールは近年ブランドも少なくなって来ています。オーデナールドOudenaardeの町にあるリーフマンス醸造所、ロマン醸造所の両醸造所が知られる所です。Clarysse醸造所(Felix Oud Bruin等)は近年廃業してしまい、Felix Oud Bruin等の銘柄はレッドビールのDuchesse...
-

ブラッセルズビアプロジェクトについて Brussels Beer Project ブラッセルズビアプロジェクトのコンセプトは"Co-Creation"。 ベルギービールの歴史に裏付けされた巧みさと冒険心、新しいクラフトビールの流れに感化された型にとらわれないビールを様々な人々との繋がりから造り出していくことにあります。彼らのベルギービールとしてのアイデンティティーは"Exploring"(探検すること)にあります。インダストリアルなビールを嫌い、「ベルギービールは本来、それぞれの醸造所がそれぞれの表現として様々な製法や原料を使いビールを長い間造り続けてきた。インダストリアルなビールが失ってしまったその冒険心を、僕らは現代に引き継ぎ表現しているんだ」と創設者のセバスチャンは語ります。もともとビールマニアでありホームブリュワーでもあったセバスチャンとオリビエの2人は、生物化学や醸造学(Biochemistry&Zymurgy)を学び、当時世界的に名の知れている会社で働いていたにも関わらず、そのキャリアをすっぱりと辞め、クラフトビールの世界に飛び込み2013年にスタートアップとして立ち上げました。ベルギーではレシピを秘密にすることを良しとするブリュワーもいる中、原材料も全て公開し、伝統的なレシピにとらわれずに醸造しています。ビール醸造以外の彼らの活動からも"Co-Creation"を感じ取ることができます。創設1年目、4種のプロトタイプを醸造し、それぞれにアルファ、ベータ、デルタ、ガンマ(英語でいうA,B,C,D・・)と名付け、試飲会をブリュッセル各所で開催。当時まだ無名だったにも関わらず、その取組みはビールファンの注目を集め、ビールに精通したブリュッセルのお客さん800人を集め、投票によりお客さんに選ばれ1位に輝いたビールを製品化しました。それがスタート時からフラッグシップとして醸造されつづけているベルジャンIPA「デルタIPA」。試飲会はその後も年に開催され、2014年は小麦をテーマにグロスバルサを選出、2016年にははじめてベルギーから飛び出し東京でも開催。セッションをテーマにしたレッドマイリップスが選出されました。設立当時、ファントムブリュワリーとして醸造していましたが、「Beer For Life」と題した、「投資をした人が毎年12本のビールを一生手に入れることができる」というクラウドファンディングでファンから資金を集め、2015年10月ブリュッセルの中心地に念願のブリューパブを設立。その後も「My Beer Project」というファンから募集したアイデアを製品化する活動を行ったり、Monthly Beerと題して様々な人々とのコラボーレーションビールを毎月生み出しています。 彼らは年間に30種以上のコラボビールを醸造し、Co-Creationのもと活動の幅をどんどんと広げていきます。日本との関わりにおいても、ブラッセルズ30週年記念「Soleil...
-

ブロウジ醸造所について Brasserie de Blaugies ブロウジ醸造所はフランス国境から、わずか数百メートルベルギー南部エノー州、ドゥールに位置する家族経営のマイクロブリュワリーです。 もともと教職だったオーナーのピエールアレックスは妻のマリーノエルと1988年に醸造所を立ち上げました。 昔ながらのクラシックなセゾンビールを造りたいと最初のビール、モヌーズはアンバーカラーのクラシックなセゾンビールにしました。またスペルト小麦を使用したセゾンデポートルはよりドライな仕上がりになっています。アメリカのヒルファームステッドとのコラボレーションビール、ヴェルモントワーズはセゾンデポートルをベースにアメリカンホップを使用し一躍注目を集めました。 現在は2人の息子がそれぞれブリュワリーと、醸造所の目の前のレストランを運営しています。ピエールアレックスいわくビールの品質が第一、急に大きくすることはしないと、その堅実な人柄で素晴らしいベルギービール、セゾンビールを造り続けています。 閉じる
-

ホフテンドルマール醸造所について Hof ten Dormaal ホフテンドルマール醸造所は、2009年に創業の醸造所兼農場です。農場は1999年からオーナーのヤンセン一家が所有しています。ブリュッセルから北、ルーヴェンに近い、ティルドンクという場所に位置しています。農場は広大な敷地で、馬や、牛、豚なども飼っています。 オーナーのアンドレさんは、アメリカで醸造設備を購入し醸造所をスタートしました。モットーはself-sustainable。出来る限り、自分の農場で取れた原料でビールを造る事。麦やホップはもちろん自分たちの手で育てたものです。副原料も使いますが、基本的に農場で取れたものを使います。 現在は家族経営でアンドレさんと2人の息子、ファーマーのドリーとブリュワーのジェフ、そして娘のリサが輸出、会計などを担当しています。 ドクトルヴァンドゥコールナール醸造所のロナルドさんから「素晴らしいビールを造るんだよ」と紹介されたこともあり輸入を開始することができました。アンドレさんとロナルドさんは親友で、月に1度程度それぞれの醸造所を訪れ、情報を共有したりしているそうです。 またアメリカ、ヨーロッパでの人気が高く、最近ではIPAや地元のベリーを使ったサワースタイルのビールなど新しいものにも挑戦しています。 2014年、不運にも醸造所が火事で焼失し大きなダメージを受けてしまいましたが、何とか再建してほしいという、一般の人々を中心にクラウドファンディングが立ち上がり、資金を集めることができました。ようやく醸造が軌道にのってきたところです。彼らのビールは原料から造るまさに「農産物」です。 閉じる...