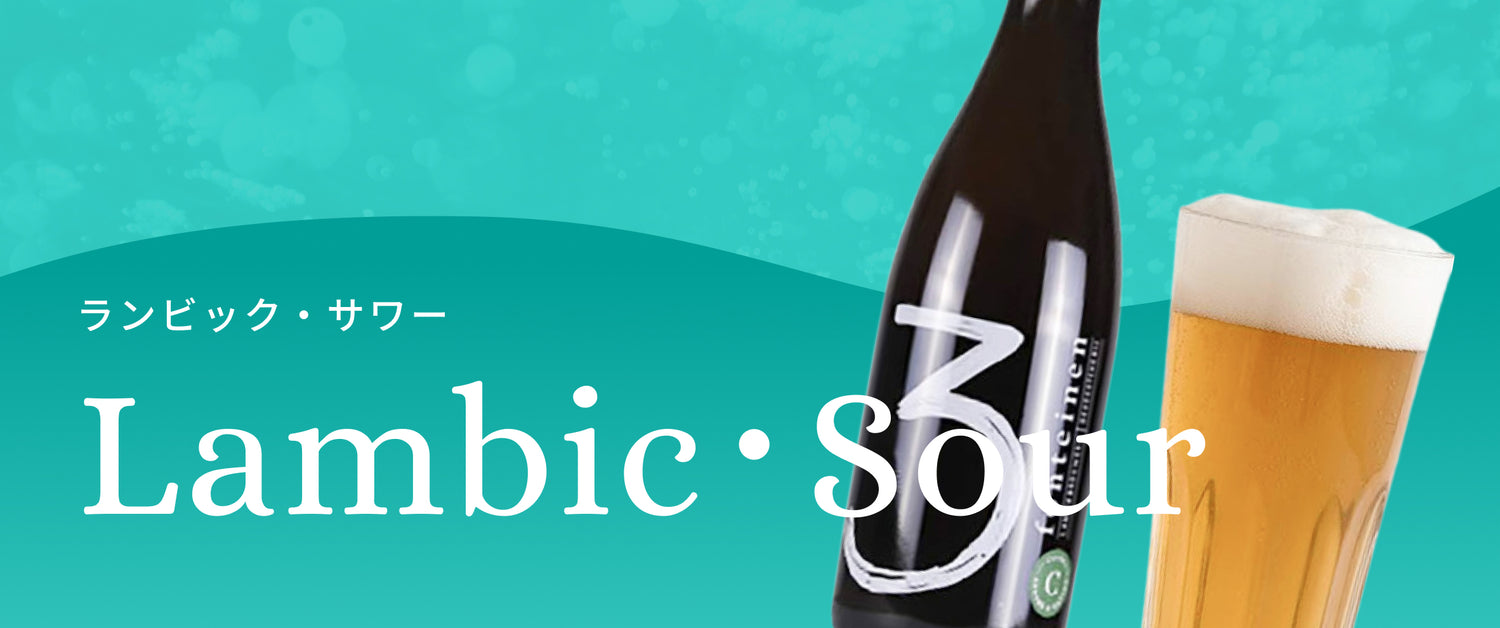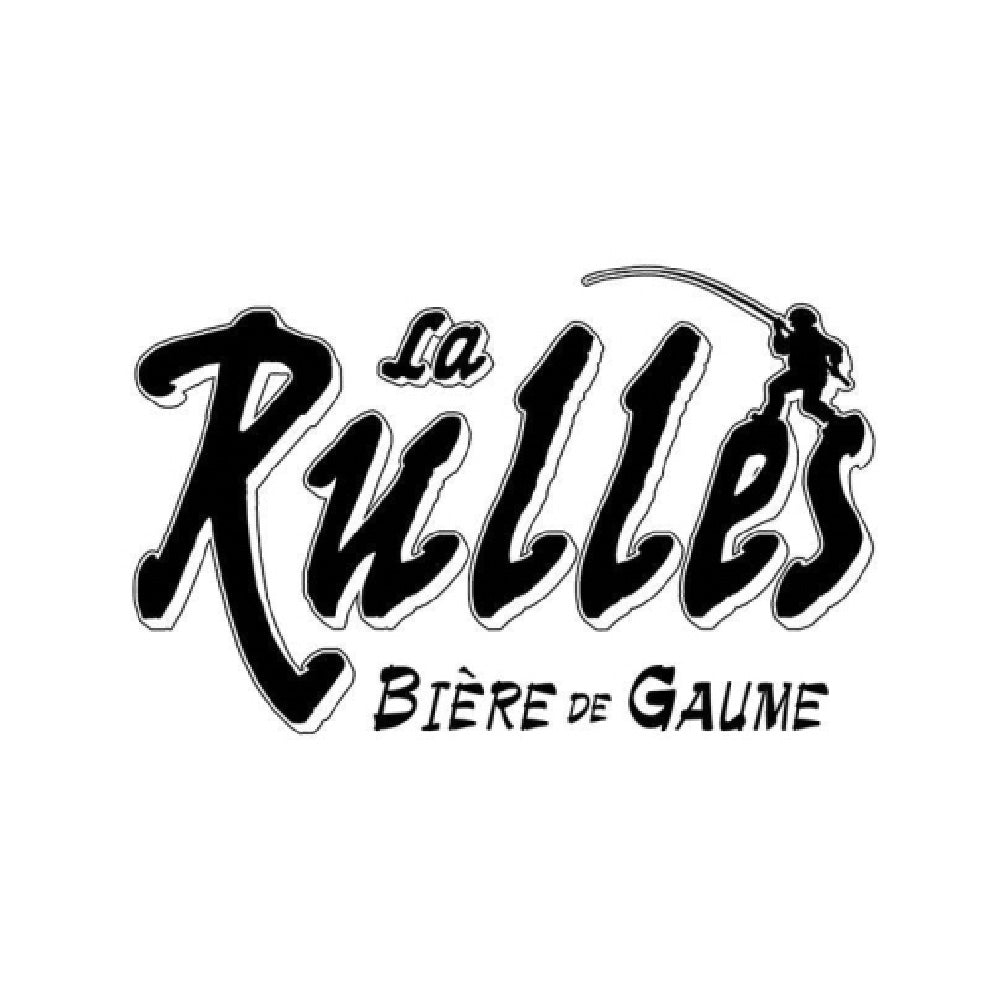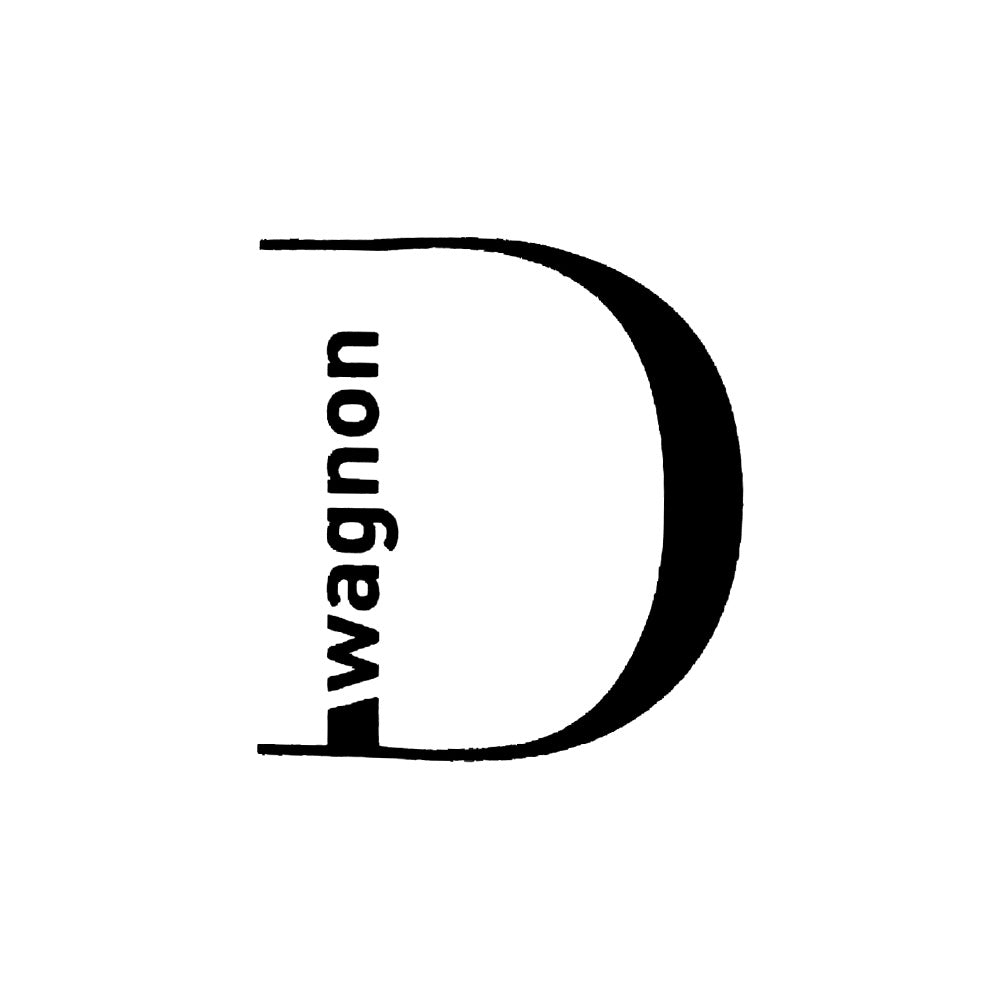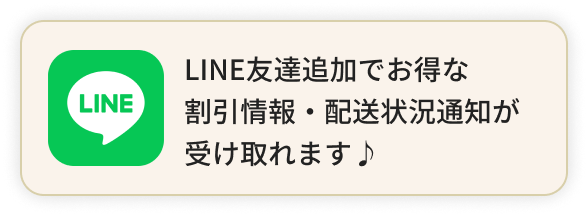Collections
-

ホワイトビールについて 小麦のビール ホワイトビールは小麦と大麦麦芽を利用するビールをいいます。本当に白いわけではないですが、小麦に含まれるタンパク質によって白濁するためにホワイトと言われるようになりました。小麦を利用するビールとしては他にもヴァイツェンビールがありますが、こちらは小麦麦芽を利用していることと、ホワイトビールがオレンジピールやコリアンダーを利用するのに比べ、ヴァイツェンはドイツの「ビール純粋令」と呼ばれる法律により、これらの副原料は利用されていません。ベルギービールの中でも世界的にホワイトビールは「ヒューガルデン」というブランドにより知られるようになります。そのヒューガルデンを生み出した「ピエール・セリス氏」。彼抜きにヒューガルデンを語ることはできません。説明して行きましょう。 閉じる
-

ボステールス醸造所について 特別なグラスにもこだわる伝統的醸造所 ボステールス醸造所は東フランダース州ブッヘンハウトという小さな町の中心部に位置します。歴史は1791年エヴァリスト・ボステールス氏が現在の地に醸造所を設立。ヨゼフが加わりその3人の息子の一人でもあるフランス・ボステールスは13年もブッヘンハウトの町長を務める名町長となりました。その後もボステールス一族が経営にかかわり、1938年に5代目のアントワーヌ・ボステールスが後を継ぐ事となります。彼は50年醸造所の発展にピルスナータイプのビール「ボステールス・ピルス」を醸造。このビールはデンテルモンドの地域以外で初めて販売されることとなり、ブリュッセルやアントワープ、ゲントに広がりました。現当主と同じ名前でもある彼は3度もブッヘンハウトの町長に選出される事となります。その息子であるイヴォ・ボステールス(6代目)と孫にあたる現当主アントワーヌ・ボステールスが7代目となって最高の味を世界へ広げることを夢見ています。この醸造所は非常に特徴的な3つのビールのみを醸造しており、シャンパンビール・デウスは醸造量の1%にも満たず、実際には2つのビールのどちらかを常に醸造しています。このような醸造所はトラピストビール「オルヴァル」などにみられる程度で歴史あるブルワリーの中でも非常に稀です。グラスにも特別なこだわりがあり世界から愛されるベルギーのビール文化を代表するブルワリーの一つです。 パウエル・クワック このビールはこの醸造所によって復刻されたものです。このフランダース地域のメッヘレンとゲントをつなぐ道中のデンテルモンド(現醸造所の隣町)にはかつてビールのラベルにも描かれているパウエル・クワックと呼ばれた宿屋「デ・ホールン」の主人がおり、彼は宿屋を経営しながらビール作りを行っていました。彼は宿屋に毎日立ち寄る郵便配達員などが馬車を降りなくてもビールを渡せるように、クワックは馬車の上でもゆっくり飲めるように馬車の側部にグラスをかけられるようにグラスをフラスコ型にデザインします。彼はそのビールを宿屋の宿泊者にもそのグラスに注いで提供することで宿も大繁盛だったと言われています。ボステールス醸造所ではいくつもの馬車を所有しており、それにはもちろんパウエル・クワックのグラスを取手にかけてゆっくりと楽しめるようになっています。 トリプル・カルメリート デンテルモンドに存在したカルメリート修道院で1679年には作られていたビールのレシピが発見され、それに基づいて醸造されており、そのレシピでは大麦、小麦、オート麦の3種の麦が使われていました。カルメリートグラスはその香りが最大限に生かされるようにデザインされており、イヴォ・ボステールスはこのグラスを軽く鳴らしてみればグラスのクオリティーが分かると語っています。 シャンパンビア「デウス」 「デウス」はラテン語で神を意味します。世界でも稀なシャンパンビアと呼ばれており、ラベルにもBrut des Flanders フランダースのブリュットと描かれています。製法は極めて特殊。一次発酵とそこから半年の熟成工程をボステールス醸造所で行い、フランス・シャンパーニュへ運びます。...
-
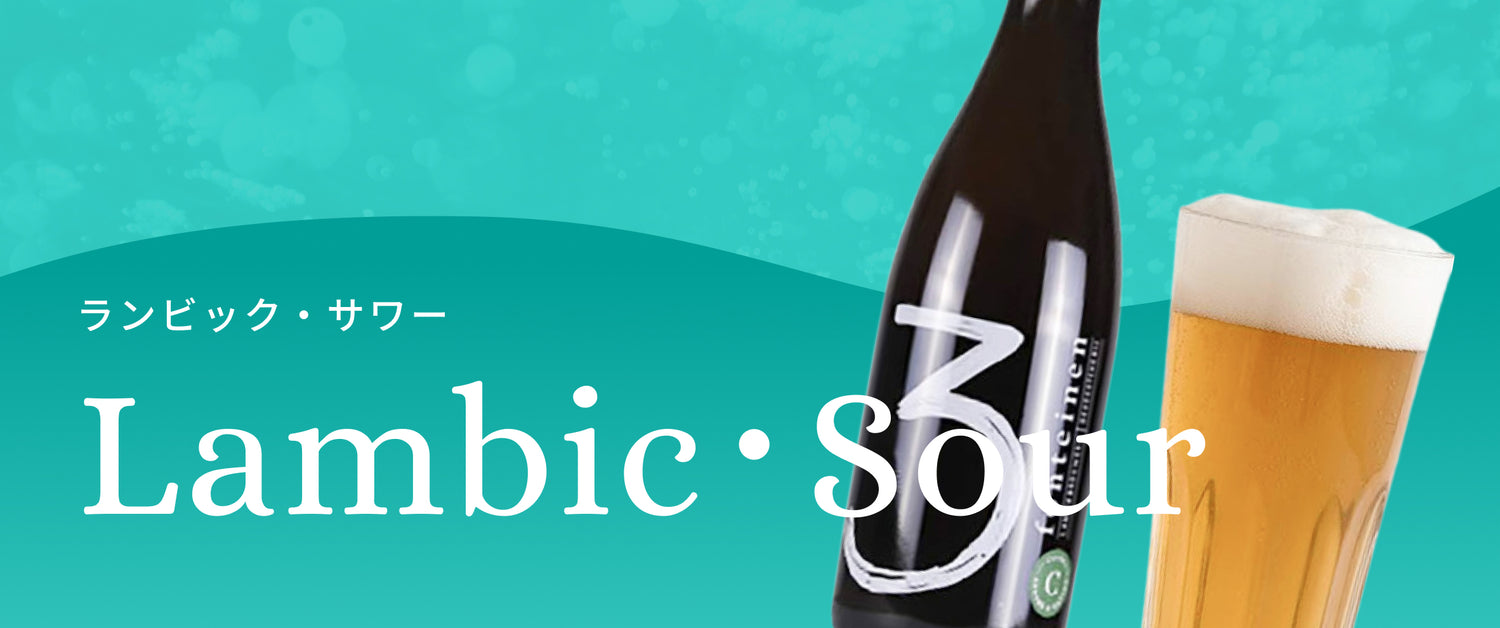
ランビックビールについて ベルギー独特の自然発酵ビール ランビックとは、ベルギーの首都、ブリュッセルの近郊のパヨッテンラントと呼ばれる地域で主に造られる、自然発酵と長期間の熟成によって独特な強い酸味を持ったビール。ランビックというジャンル名は、「レンベーク」という地名から名付けられたとされ、この地域に流れる「ジネ川」付近に生息するとされる野生酵母によって発酵が行われる。リンゴの外果皮の野生酵母で発酵させた伝統的なシードルにも通じるものがある味わいです。若いランビックと古いランビックをブレンドしたグーズやフルーツを加えて発酵させたものなど様々な種類が存在します。別の話であるがゼネ川はこの地域ではZinneジネ川と呼ばれ、その地域で創業した現デ・ラ・セーヌ醸造所(現ブリュッセル)のジネビアにも描かれています。 ランビックの特徴的な醸造 1.ランビックは大麦麦芽と小麦、香りや苦みを飛ばすために2~3年寝かせた古いホップを用いる。雑菌による汚染のリスクを抑えるために冬場のみ醸造が行われる。2.煮沸した麦汁を「クールシップ」と呼ばれる浅い冷却槽に麦汁が流され、一晩放置することで冷却する。屋根や壁には穴が開けられ風が吹き抜けるようになっており、木材にも野生酵母が住み着いているとされる。3.発酵の始まった麦汁を木樽に移し、1年~3年の間熟成させる。樽の内側に住み着く野生酵母によって、麦汁の糖分は熟成が長くなるほど少なくなり独特な香り(埃っぽい、獣くささなど)が増す。4.ランビックの特徴的な醸造に深く関わる野生酵母の代表的なものとして、以下が挙げられる。 ・ブレタノマイセス・ブリュセレンシス(Brettanomyces bruxellensis)・ブレタノマイセス・ランビクス(Brettanomyces lambicus) ランビックのスタイル ストレートランビック熟成させたランビックの「原酒」。炭酸ガスによる発泡はほぼない。ベルギー国内では流通することもあるが、基本的に海外への輸出はされていない。...
-

ルフェーブル醸造所について Brasserie Lefebvre ルフェーブル醸造所はブリュッセルの南西部、ワロンブラバント州クエナストにある中規模醸造所です。 このあたりには、昔大きな石切場があり多くの労働者が働いていました、今でもその名残を見ることができます。 1876年に初代ジュールスルフェーブルが石切場で働く労働者の疲れと、渇きを癒すためにビアカフェを作り、醸造を開始しています。 今では5代目のフィリップ、6代目のポールが責任者として運営、安定した品質とバランスの良さで好評を得て、ベルギー国外への輸出も伸びています。 現存するナミュール郊外のフローレフ修道院のビールライセンスは、1983年にルフェーブル家に託され、今では醸造所のメインブランドになっています。小便小僧をラベルに用いたホワイトビール、ブロンシュドブリュッセルやはちみつを使用したバルバールも男女問わず人気の高い銘柄です。 美味しいビールを造る秘訣は良いモルトを使うことと掃除。代々言い継がれているそうですが、規模が大きくなってもその精神は変わらないそうです。 閉じる
-
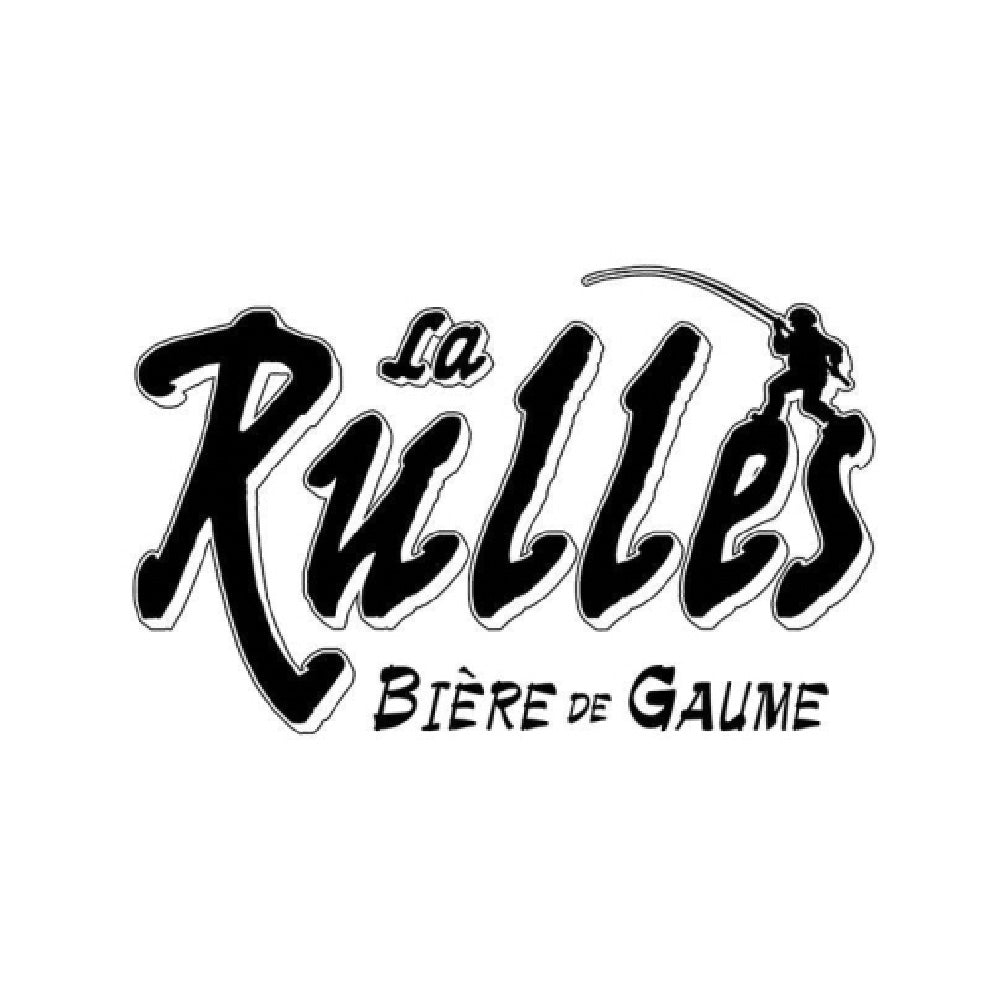
ルル醸造所について ベルギー・ルクセンブルグ州の小さな醸造所 ルル醸造所はベルギー南部のルクセンブルグ公国に隣接するルクセンブルグ州のゴーム地区にてグレゴリー氏が1998年に商売としての醸造を開始したのが始まり。ホップはアメリカ、シアトル近郊のヤキマ産を使用。醸造タンクは蒸気などではなく直火にこだわります。発酵は通常はタンク内で行いますが、ここでは発酵室を作り発酵釜の上部を完全に解放して行う。りんごや洋梨のような香りがこれほどただよう発酵室はめったにありません。醸造過程にも一つ一つ違いがあり、それがこのビールの特別な味わいを生み出す理由です。 車で20分ほどのオルヴァル修道院から酵母を譲り受ける もう一つは酵母。ルル醸造所から20kmにあるオルヴァル修道院から酵母を譲り受けたのが始まりで、発酵の終わりに酵母を取り出して使い続け、独自の酵母に変化しているとグレゴリー氏は語っている。彼自身、以前のオルヴァル修道院の醸造方法に多大な影響を受けており、発酵釜の上部を開放して酵母にストレスをかけないベルギーの昔ながらの発酵方法を行っているのが大きな特徴です。 実は当初、彼はルル・ブロンドのみしかビールを作る気がありませんでしたが、彼の気が変わり、ルル・ブラウン、ルル・トリプルと新しいビールを醸造する事になり、夏にはルル・エスティバル(夏)というビールも発表しています。ベルギーのデリリウムカフェでも必ずルル醸造所のビールを提供しています。樽生も二次発酵、無濾過にて行っており、ルル醸造所やジャンデラン醸造所、デ・ランケ醸造所、カンティヨン醸造所やデ・ラ・セーヌ醸造所はお互いに尊敬しあい、小さな醸造所同士で協力しあっています。 閉じる
-

-